ペットと住まいの寄り添いトレーナー 佐藤👨です。千葉県東葛地区を起点にペットショップと連携しながら対応。オンラインを駆使した家庭犬専門しつけの教室。しつけ以外に、犬の特性に基づいた飼い方、住まいでの環境設定他幅広に情報提供しております。他にない犬知識提供のオンラインセミナーと併せ、褒める実技指導を行っています。

犬の社会性は、生後のごく初期段階で形成されます。特に、生後3週齢から14週齢の間は「社会化期」と呼ばれ、犬が外界の刺激を受け入れ、学び、適応していくために極めて重要な時期です。この時期に、他の犬や人間、環境、音、匂いなどに慣れさせることが、その後の行動や性格を大きく左右します。なかでも「他の犬への慣らし」は、犬の一生を通じての社会的安定やストレス耐性、攻撃性の抑制に直結する大切な要素なんですよね。
1.社会性の基礎を築く時期にしか学べないことがある
子犬の脳は、生後間もなくから急速に発達し、環境刺激に対して柔軟に対応できる「学習の黄金期」を迎えます。この時期に他の犬と触れ合うことで、犬同士のボディランゲージや距離感、遊び方、上下関係の取り方を自然に学習していきます。
たとえば、噛む強さを加減する咬み抑制も、兄弟犬や母犬との遊びを通じて覚える重要なスキル。相手が痛がる反応を見て「これ以上はやりすぎ」と理解する。これを学ばないまま成犬になると、興奮した際に相手を強く噛んでしまうなど、トラブルにつながる可能性が高まります。つまり、他の犬と関わる経験は「犬としての言葉を学ぶ」時間となります。
2.社会的恐怖の芽を防ぎ、精神的に安定した犬に育つ
社会化期に十分な刺激を受けずに成長した犬は、未知の存在に対して過敏に反応しやすくなる。特に他の犬を「脅威」として認識してしまうと、散歩中に吠えたり、近づけないほど怯えたり、あるいは防衛的に攻撃するような行動を取ることがあります。
一方、子犬のうちから穏やかな成犬や同世代の犬と安全に触れ合う経験を積んだ犬は、「犬という存在は怖くない」「正しく接すれば楽しい」と感じるようになる。この安心感が、のちの生活のあらゆる場面で落ち着きや安定した行動につながっていく。
人間の子どもと同じく、犬も“未知への恐怖”が最も強く形成されやすいのは幼少期なのです。その時期に「慣れ」と「楽しさ」をセットで体験させることで、恐怖の回路が作られにくくなると思います。
3.問題行動の予防につながる
他の犬に慣れていない犬が成犬になると、さまざまな問題行動が表れやすくなる。代表的なのは「吠え」「威嚇」「咬みつき」「極度の緊張・逃避」です。
たとえば、ドッグランで他の犬が近づいてきた時に過度に興奮し、吠え立ててしまう犬は、「他犬=刺激が強すぎる存在」として認識している。これは社会化不足の典型例。
子犬のうちから他の犬に慣れさせると、「犬との関わり=普通のこと」として受け止めるため、必要以上に反応しなくなる。結果として、リードを引っ張る、吠える、威嚇するなどの行動が減り、飼い主にとっても散歩が快適になる。
4.犬同士のルールを学ぶことで、トラブルを避けられる
犬社会には、人間には見えにくい「犬同士のルール」が存在と考えられています。例えば、目線の合わせ方、体の向き、尻尾や耳の動き、そして相手への距離の取り方。これらの微妙なサインを読み取る力が、他犬とのトラブル回避に直結します。
子犬のうちから他犬と遊ぶ機会を持つことで、そうしたボディランゲージの“読み取り”と“発信”の両方を学ぶ。これにより、相手犬が嫌がっていることに気づいたり、逆に「自分がやりすぎた」と理解したりできるようになる。これは、人間が教えられることではなく、犬同士の経験からしか得られない貴重な学びなのです。
5.動物病院やドッグランなど、社会生活への適応が可能になる
現代社会で暮らす犬は、他の犬と出会う機会が非常に多いです。動物病院、トリミングサロン、ドッグラン、ペットホテルなど、他犬が存在する環境は日常的になっています。
こうした場面で他の犬を過剰に怖がったり、攻撃的になったりすると、犬自身にも強いストレスがかかり、飼い主にとっても大きな負担となります。
子犬のうちから他犬と慣れ親しんでおけば、そうした場面でもリラックスして過ごせるようになり、スタッフや他の飼い主との関係もスムーズに築ける。結果として、犬の生活の質(QOL)も向上すると思います。
6.他の犬から学ぶ「自己コントロール」
子犬同士、あるいは成犬との触れ合いを通して学ぶ大きな要素のひとつが「自己コントロール」。
犬は遊びの中で「相手に合わせる」ことを自然に学ぶ。
例えば、体格差がある場合、強い犬は弱い犬に合わせて力加減をする。遊びが行き過ぎれば、相手から無視されることもあると思います。
こうした経験を通じて、「自分の行動が他者にどう影響するか」を理解し、社会的なバランス感覚を身につける。この能力は、後のしつけやトレーニングにも良い影響を与える。落ち着いて他犬を観察できる犬ほど、飼い主の指示に集中できる傾向が強いのです。
7.他犬との慣らし方の実践ポイント
ただし、「他の犬に慣らす」といっても、無計画に近づけるのは逆効果である。
他犬との慣らしには次のようなステップを踏むことが重要。
- ワクチン接種が完了するまで、無理な接触は避ける。
それまでは安全な距離から「見るだけ慣らし」を行う。 - 穏やかな成犬や社会性の高い犬を相手に選ぶ。
攻撃的な犬や落ち着きのない犬とは、初期段階では接触させない。 - 短時間で終わらせる。
最初は数分程度で十分。子犬が緊張しすぎないうちに切り上げる。 - 良い印象を結びつける。
他犬を見たり接触した後に、おやつを与えて「他犬=いいことが起きる」と関連づける。 - ドッグトレーナーやパピーパーティーを活用する。
管理された環境で、犬同士の社会化を専門家の指導のもと行うのが理想的。
子犬のうちから他の犬に慣らすことは、単なる「遊び」ではなく、「犬として健全に生きるための社会教育」でもあります。この経験によって、犬は他者を尊重し、自己をコントロールし、安心して暮らせる心の基礎を築いていきます。逆に、社会化不足のまま成犬になると、恐怖や攻撃性、ストレス行動など、多くの問題を抱える可能性が高まってしまうのです。
犬の一生は、飼い主の手でどう育てるかによって穏やかにも不安定にもなってしまいます。
だからこそ、子犬の時期に「他の犬との慣らし」を意識的に行い、豊かな社会性を育むことが、最も重要な要素なのです。
まずは、無料相談してみたい方のお申し込みはこちらからどうぞ。
●一人で悩みを抱え、相談する先がわからないお客様はこちら!
<オンライン相談(30分) 無料>
https://ldplus.jp/contact/pets/
オンラインしつけ勉強会のお申し込みはこちらからどうぞ。
●飼い主様自身ができるようになるしつけの基本がわかる
<オンライン勉強会(60分) 有料(1,000円税込)>
https://forms.gle/9ruE5RcNEigM9ZX76
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・
全体ホームページ(様々なご提供中サービスをご覧いただけます)
人とペットに優しい、ライフデザインの実現を!
Life Design Plus 代表 佐藤 篤
https://ldplus.jp/
公式ライン:コロル Doggy Training
(家庭小型犬オンライン&出張しつけ)
https://lin.ee/gp1wRpw
【お問合せ先】
mail: boby160719@gmail.com
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

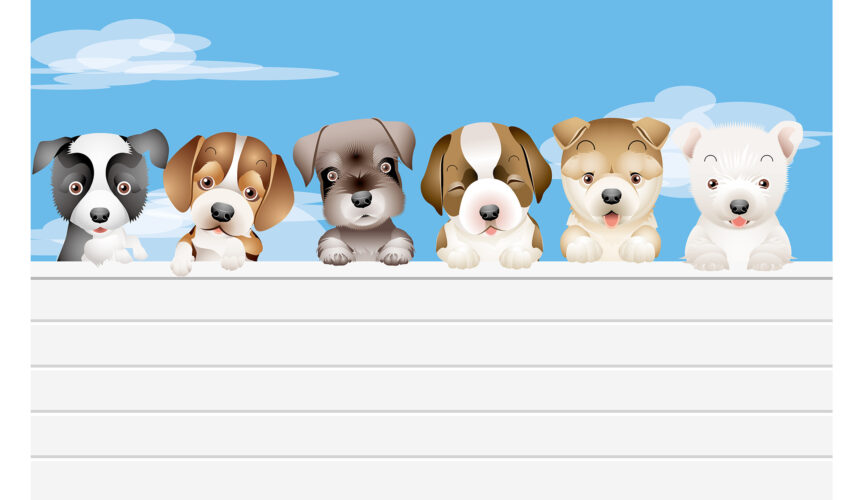


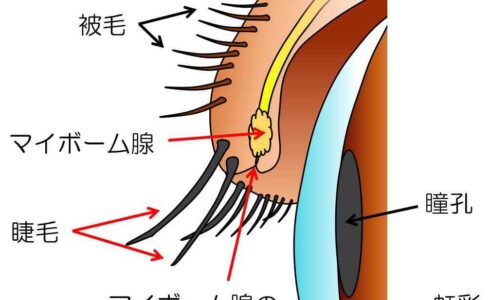
.jpg)


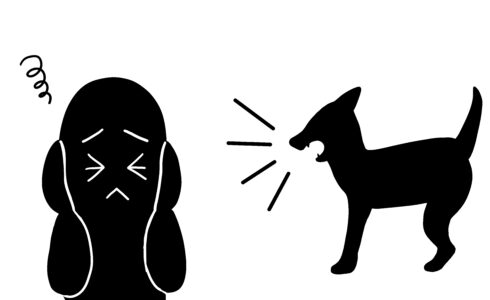
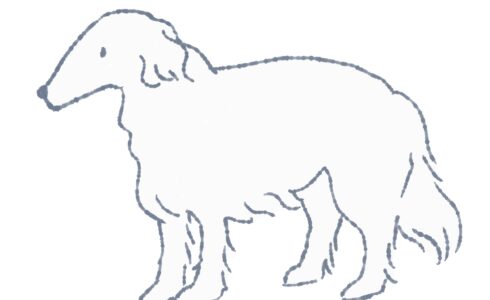
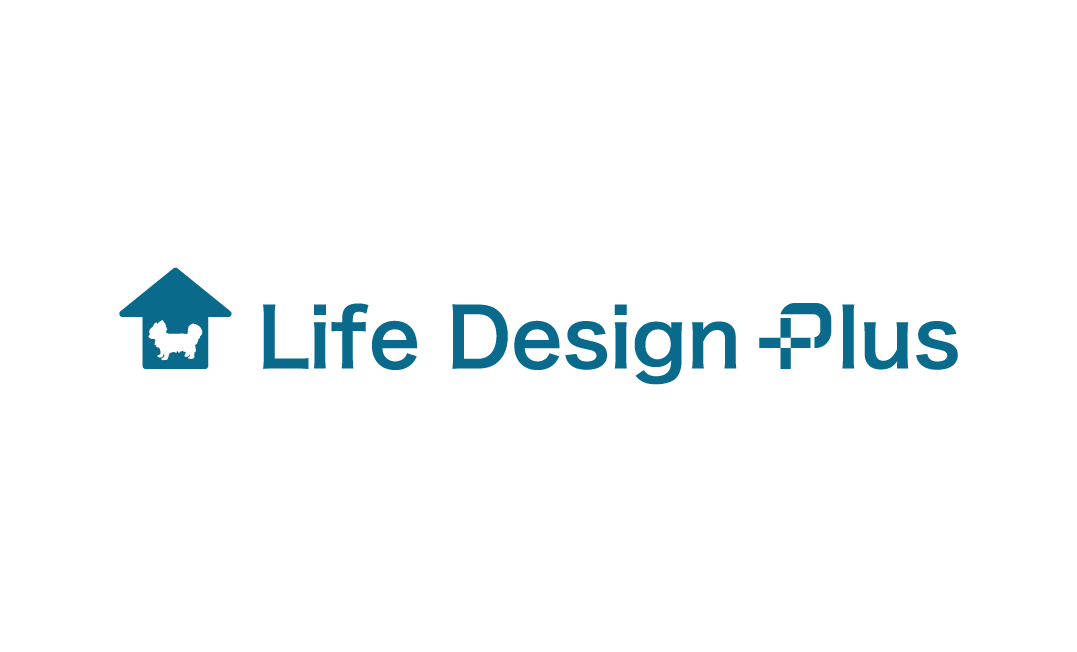
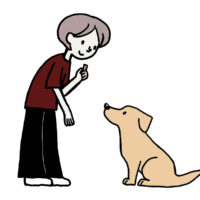





この記事へのコメントはありません。